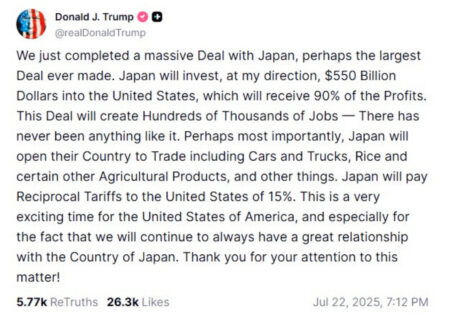誰ひとり取り残さない不登校対策の推進について

※最下部に要約があります。
令和7年 第二回定例会 一般質問
【村本修司議員質問】
誰ひとり取り残さない不登校対策の推進についてお伺いします。
県内の不登校児童生徒数は、令和4年度に9,263人と増加傾向が続いていましたが、令和5年度には8,703人と減少に転じました。これは、県教育庁が進めてきた校内フリースクール設置や教育相談体制の充実など、多面的な取り組みの成果であり、尽力に心より敬意を表します。
一方で、支援が届かない子どもがいることも事実です。校内フリースクールは「学校に来られる」ことが前提で、校門に近づくことすら難しい子どもには利用が困難です。
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、フレックス高校において、高校生が大学生に相談できるキャンパスエイドという事業、など相談体制の充実により、早期対応は進んでいますが、不登校が長期化した子どもには支援が十分届いていない例も見られます。
こうした中、水戸市で開校した私立リリーガーデン小学校の取り組みは注目されます。自然体験や探究学習を取り入れ、「学びたいけれど学校に行けない」子どもに新たな学びの場を提供する、「学びの多様化学校」のモデルです。
我々県議会公明党での現地調査では、学校説明会では校門の外から覗いていた子が、入学後数日で耕運機を操作して畑を耕す姿が印象的で、不登校の苦悩からの大きな変化を感じました。東京から移住した家庭もあり、同校の柔軟で魅力的な教育方針が共感を呼んでいることがうかがえます。
全国には現在58校の「学びの多様化学校」があり、その約6割は公立です。国も設置準備に対する補助制度を設け、分教室型やコース型など柔軟な形が認められています。
県として校内フリースクールを進める方針は理解しますが、「どの学校にも行けない」児童生徒が一定数いる以上、さらに柔軟で抜本的な選択肢が必要です。公立での「学びの多様化学校」の設置、あるいは私立設置への運営費補助などを支援し、不登校を一人でも減らすための実効性ある手立てを今こそ打つべきです。
学びたい子どもが安心して学べる環境を、県として責任を持って整備いただくよう強く要望します。
次に重要なのは「信頼できる大人との出会い」をどう生み出すかです。相談に訪れる子どもは、自分の状況を言葉にできる一部の子どもたちであり、相談すら難しい子どもたちにも目を向けるべきです。
NPO法人パノラマの石井理事長は、「親でも先生でもない、暇そうで話しやすい大人の存在」が大切だと述べています。茨城県ではキャンパスエイドとして相談できる大学生が高校に派遣されていますが、神奈川県の高校では、そうした大人が常駐する「校内居場所カフェ」が設けられ、たわいもない会話や遊びを通して“信頼貯金”が蓄積され、初めて相談につながると聞きます。
県内でも、高萩高校でNPO法人茨城居場所研究会が月1回「居場所カフェ」を開いており、私も見学しました。生徒はちょっとしたお菓子や飲み物を楽しみながら自然体で会話を交わし、時には自分のタイミングを計って相談するそうです。
このような取り組みは、児童生徒の居場所づくりとして非常に有効であり、不登校の未然防止にも繋がると思います。こうした活動を行う民間団体への支援やフレックス校への積極的な設置をお願い申し上げます。
以上を踏まえ、誰ひとり取り残さない不登校対策の推進について、教育長にお伺いします。
【教育長答弁】
誰ひとり取り残さない不登校対策の推進についてお答えいたします。
現在、全国の不登校児童生徒数は年々増加し、2023年度の文部科学省の調査では過去最多となっております。
これまで、県では、民間フリースクールに対する運営費補助や、校内フリースクールの設置促進など、学校内外の学びの場や居場所の確保に取り組んでおり、昨年度末で、県内に民間フリースクール61施設、校内フリースクール159校が整備されております。
民間フリースクールでは、学校への登校を再開したケースや高等学校に進学できたケースなどの報告を受けており、校内フリースクールでは、利用したことにより不登校になることを未然に防いだ事例が多く報告され、その結果、本県の不登校児童生徒数は、全国で唯一減少いたしました。
さらに、高等学校において、フレックス高校に不登校生徒の支援として、心理学を専攻している大学院生などがキャンパスエイドとして、生徒と相談できるスペースを設置し、学校に安心できる居場所作りを進めており、中学校まで不登校だった生徒が、登校するようになるなど一定の成果をあげております。
しかしながら、依然として不登校児童生徒が多いことを考えますと、引き続き支援の充実に努めることが重要であります。
その支援の一つである「学びの多様化学校」は、新たな学びの場の選択肢の一つでございますが、公立での設置にあたりましては、児童生徒の通学距離や時間などを考慮する必要がございます。
市町村の教育支援センターからは、保護者の送迎がなければ通うことができないといった通学方法に課題があると聞いておりますことから、今年度開校した「学びの多様化学校」への訪問や情報交換を実施し、成果や利用者の声を把握するとともに、引き続き、他県の状況を注視し、市町村が設置する場合の支援の在り方などについて研究してまいります。
なお、私立学校への支援については、それぞれが建学の精神に基づく特色ある教育を展開し、不登校対策にも主体的に判断して取り組んでいるため、「学びの多様化学校」の設置に限らず、広く不登校対策に対して、運営費に対する補助である経常費補助金を加算し、取組を支援しており、今後も継続してまいります。
また、議員からご提案のありました高萩高校の「居場所カフェ」では、地域のボランティアの方に運営していただいており、フードバンクから頂いたお菓子や飲み物を提供し、不登校生徒の支援にとどまらず、生徒たちの居場所づくりの一役(いちやく)を担っております。
学校からは、「安心できる大人と交流する中で、生徒の達成感や自己肯定感、自己有用感を実感できる空間になっている」との声があり、小中学校で不登校を経験している生徒が、悩みを相談する場にもなっていることから、こういった民間団体と連携した取組について、効果や手法を周知し、学校の実情に応じて実施されるよう積極的に働きかけてまいります。
県といたしましては、これらの様々な取組を通じて、多様な学びの場や居場所の確保と充実に努め、誰ひとり取り残さない不登校対策をしっかりと推進してまいります。
【村本修司議員感想・要望】
ご答弁ありがとうございます。
学校に行けない子どもにも学びの場を保障するため、公立での『学びの多様化学校』の設置や私立への運営費補助を含め、子ども一人ひとりに寄り添った実効性ある対応を強く求めます。
社会課題の多くは、制度の狭間や想定外の現場で静かに進行しています。そこで何が起きているのか、私は今回、地域の声と向き合いながら質問を考えました。そこには「支援が足りない」という叫びと同時に、「もっと良くしたい」という現場の挑戦もありました。政策とは、制度と熱意の交差点にこそ命が宿ると思っています。課題を機会に変え、挑戦する現場をともに支える茨城県であってほしい。と願い、質問を締めくくります。
以下ChatGPTによる要約です。
■ 村本修司議員質問
- 成果と評価
- 県内の不登校児童生徒数は2022年度9,263人→2023年度8,703人に減少。多面的な県の取組に敬意。
- 課題の指摘
- 校内フリースクールは「登校できる子」が前提。長期化・深刻化した不登校児童生徒への支援が届いていない。
- 校門にも行けない子や、相談すら難しい子に焦点を当てる必要。
- 政策提案1:学びの多様化学校
- リリーガーデン小学校など、自然体験・探究型の新たな教育モデルが注目。
- 国の制度では公立設置も可能。分教室型・コース型も柔軟に認可されている。
- 公立での設置支援、私立設置への運営費補助を求める。
- 政策提案2:信頼できる大人との出会い
- 高萩高校などの「居場所カフェ」による民間連携型の居場所支援を紹介。
- 神奈川県の「校内居場所カフェ」事例を引き合いに、たわいもない交流の重要性を強調。
- 民間団体支援や居場所支援の拡充を要望。
■ 教育長答弁
- 現状と成果
- 県内には民間フリースクール61施設、校内フリースクール159校を整備。
- 登校再開や進学、不登校未然防止といった成果が多数。
- フレックス高校でのキャンパスエイドも一定の成果。
- 「学びの多様化学校」への姿勢
- 学校選択肢の一つとして有意義と認識。
- 公立設置には通学距離・手段の課題あり。
- 本年度の新設校を訪問し、効果・ニーズを調査予定。
- 私立校への支援は運営費補助の加算で対応中。今後も継続。
- 「居場所カフェ」への対応
- 高萩高校での事例を評価。「安心できる大人」との関わりが自己肯定感等の向上に寄与。
- 他校でも実施できるよう、効果や手法を周知し働きかける。
- 今後の方向性
- 多様な学びの場と居場所の確保を通じて、「誰ひとり取り残さない」不登校対策を推進する。
■ 村本修司議員感想・要望
- 制度の整備だけでなく、現場の「支援が足りない」「もっと良くしたい」という声と熱意に応える施策を求める。
- 子ども一人ひとりに寄り添う具体的かつ実効性ある対応、公立・私立問わぬ支援の充実を強く要望。
- 「制度と熱意の交差点」にこそ政策の命が宿る。挑戦する現場を支える茨城県であってほしい、と締めくくる。
#茨城県議会 #日立市