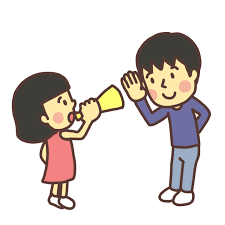医師の地域偏在や診療科偏在に対する対応について

※最下部に要約があります。
令和7年 第二回定例会 一般質問
【村本修司議員質問】
医師の地域偏在や診療科偏在に対する対応について伺います。
茨城県では、医師の不足が長年の課題となっています。人口10万人あたりの医師数は全国平均を下回り、特に県北・鹿行地域では深刻な状況であるとされております。
これまで、県では、地域枠の活用、医師派遣、修学資金貸与制度、さらに「最優先で医師確保に取り組む医療機関・診療科」の指定による数値目標の設定など、本当に様々な対策を行っていただいています。そのおかげもあり、県内の医師数は年々増加し、2022年時点では、6,029人と、10年前と比べて約17%増となっております。
一方、厚生労働省は令和2年に全国ベースで医師数の多寡を統一的かつ客観的に比較・評価するための指標として都道府県および二次保健医療圏ごとの「医師偏在指標」を算定し、指標の上位3分の1を医師多数地域、下位3分の1を医師少数地域に区分することとなりましたが、本県は全国第43位の医師少数県とされております。
しかしながら、私は、医師不足とは単に“医師数が少ない“状態ではなく、「必要な医療が、必要な場所で、必要なタイミングで受けられない」ことを意味すると考えます。例えば、がんなどの高度医療であれば、時間をかけて通院することを不便と感じない方もいますが、感染症や産科など日常的な診療で長距離通院は生活に支障をきたし、「医師不足」として実感される場面です。加えて、救急搬送時間の長さも、住民の不安や不満を引き起こす要素の一つです。そのため、私は、例えば、住民へのアンケートなどを通じて医療に対する県民の「満足度」を調査し、政策の指標とすることも必要ではないかと考えています。
医師偏在指標では、あくまで全国や他地域との相対的な比較しかすることができません。本県の医師数がいくら増えたとしても、他の都道府県の医師数が同様に増えれば、いつまでたっても医師少数県に留まることとなってしまいます。
もしかしたら、供給過剰な状態になってしまう可能性も否定できません。
さらには、これからは診療科の偏在についても対応していく必要があると考えます。県全体として医師が不足しているのであれば、全ての診療科の医師を一様に増やしていくことは現実的ではないかもしれません。
このようなことから、県には、医師偏在指標が全国平均に追いつくように、単に医師数を増やすのではなく、地域別や診療科別の医療のニーズを把握したうえで、医師の地域偏在や診療科偏在の是正に取り組んでいくことが求められます。
以上を踏まえ、医師の地域偏在や診療科偏在に対する県の対応について、保健医療部長にお伺いします。
【保健医療部長答弁】
医師の地域偏在や診療科偏在に対する対応についてお答えいたします。
医師の偏在指標でございますが、都道府県や二次保健医療圏ごとの人口構成、患者の流出入、医師の性別・年齢構成などを用いて算出されているものの、地域内に所在する医療機関の数や規模などは考慮されておりません。
このため、この指標はあくまで全国順位を基準といたしました相対的な目安に留まるものと認識をしておりまして、厚生労働省もその指標の利用に当たって相対的なものであるということを述べております。一方で、県内の二次医療圏の間で差が生じているということも事実だと認識をしております。
これまで、本県では、地域枠など、修学資金貸与制度などによりまして、県内の医師不足地域を中心に勤務する医師を養成することで地域偏在の是正に取り組んでまいりました。
特に、地域枠につきましては、2009年度に筑波大学で5名の定員を設置して以降、順次拡大をさせていただきまして、2025年度の定員は全国トップクラスの11大学70名となっております。
これらの取組によりまして、本県の全体の医師数でございますが、国の推計において、2036年度の必要医師数を充足することとされておりますが、地域偏在については依然として残ることが見込まれております。
このような中、更なる地域偏在の是正に向けまして、2020年度の地域枠入学者からは、修学資金の返還免除要件において、これまで教育機会を確保するために医師不足地域として取り扱ってまいりました水戸保健医療圏を、先に申し上げた医師偏在指標に基づきまして医師不足地域「外」とさせていただいたほか、2025年度の入学者からは、臨床研修を修了した3年目以降の医師、7年間残りの義務年限があるわけですが、そのうちの4年半以上を医師不足地域において勤務する制度に改正をさせていただきました。
これにより、今後、つくば、水戸、土浦医療圏以外の医師不足地域に勤務する修学生医師が着実に増加していくと考えられることから、地域偏在は徐々に是正に向かうものと考えております。
さらに、ワークライフバランスを重視する若手医師の増加に伴い、外科をはじめとした政策医療を担う診療科を選択する医師が減少傾向にあるなど指摘をされております。今後、そういった診療科偏在についても対応していく必要があると承知をしております。
県といたしましては今後、単に医師数を増やすのではなく、救急、小児、周産期などの政策医療分野の医療提供体制を確保する観点から、地域における各医療機関の役割に加えまして、入院・外来患者数や救急搬送件数などの客観的なデータを踏まえた上で、必要な医師の養成・確保に取り組んでいく必要があると認識をしております。このためにも、国に対しまして、中央要望や全国知事会を通じまして、地域別・診療科別に真に必要な医師数とはいかなるものか、ということの算定を要望しているところであります。
また、県、大学、医療機関が一体となって政策医療を担う医療機関への医師派遣、これを支援する「医師配置調整スキーム」というものを運用しておりますが、これは、二次保健医療圏ごとに設置をされた地域医療構想調整会議、これとも連携をさせていただいて、各医療機関が地域において担っている役割に加えまして、先に述べさせていただいた客観的なデータに基づきながら、医師派遣の必要性について協議をしてきているところであります。
県といたしましては、引き続き、地域医療構想における各医療機関の役割分担や連携に係る協議を進めさせていただくとともに、それぞれの医療機関が自らの役割・機能を適切に発揮するために必要な医師の確保を支援することにより、医師の地域偏在及び診療科偏在の是正を図りまして、全ての県民が安心して医療を受けられる体制を整備してまいります。
【村本修司議員感想・要望】
ご答弁ありがとうございます。
医師数の増加だけでは、必要な医療を必要な場所で受けられるという県民の実感にはつながりません。地域別・診療科別の実態を把握し、真に求められる医療を届ける偏在是正をお願いします。それにより地域により命の重さに違いが出ないよう強く要望します。
以下ChatGPTによる要約です。
■ 村本修司議員質問(要約・箇条書き)
- 医師不足の現状
- 茨城県の医師数は全国平均を下回り、特に県北・鹿行地域で深刻。
- 対策として地域枠、修学資金貸与、数値目標設定等により、医師数は10年で約17%増(6,029人)。
- 医師偏在指標の課題
- 医師偏在指標では相対評価にとどまり、県内医師数が増えても順位は上がらない可能性あり。
- 真の医師不足とは「必要な医療が必要な場所・タイミングで受けられない」こと。
- 具体的な課題認識
- 高度医療は遠距離通院も許容されるが、産科・感染症などでは支障が大きい。
- 救急搬送時間も不満要因。
- 医療「満足度」の県民アンケートの活用を提案。
- 今後の視点
- 全体の医師数増だけでなく、診療科別・地域別ニーズに応じた偏在是正が必要。
- 無計画な供給過剰にも注意。
- 政策としての重点的な配置が重要。
■ 保健医療部長答弁(要約・箇条書き)
- 指標の認識と限界
- 医師偏在指標は相対的指標で、医療機関の数や規模は反映されない。
- 県内でも二次医療圏ごとの差は現実に存在。
- これまでの取り組み
- 地域枠・修学資金制度により、医師不足地域へ人材確保を進めてきた。
- 地域枠は2009年度5名→2025年度70名に拡大(全国トップクラス)。
- 医師数は2036年度に必要数を充足見込みだが、地域偏在は残存。
- 地域偏在への新たな対応
- 2020年度以降、水戸圏を医師不足地域「外」に変更。
- 2025年度入学者からは義務年限中4年半以上を不足地域勤務に設定。
- 診療科偏在への認識
- 外科等の政策医療を担う診療科の志望者減。
- 救急・小児・周産期など特定分野の医師確保が課題。
- 今後の方針
- 各医療機関の役割、患者数・救急搬送件数などのデータを基に、診療科別医師確保を推進。
- 国に対し、地域・診療科別の必要医師数の明確化を要望。
- 「医師配置調整スキーム」を活用し、医療構想調整会議と連携。
- 医師の役割・機能の明確化と確保により偏在是正を進める。
■ 村本修司議員感想・要望(要約)
- 医師数の増加では「医療が受けられる実感」につながらない。
- 地域・診療科別の実態把握を重視し、命の格差が生まれない偏在是正を強く要望。
#茨城県議会 #日立市