子どもアドボカシーの推進に向けた県のビジョンについて
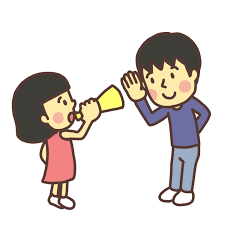
※最下部に要約があります。
令和7年 第二回定例会 一般質問
【村本修司議員質問】
子どもアドボカシーの推進に向けた県のビジョンについて伺います。
子どもアドボカシーは、子どもが意見を表明し、権利を守るための支援活動であり、大人がその声を尊重する環境づくりが重要です。
これを担う「アドボケイト」は、子どもの気持ちや意見の整理と発信を支える役割を担います。
国も令和6年4月施行の改正児童福祉法で、子どもの意見表明支援事業を都道府県の業務と位置づけました。
私もこれまで何度か取り上げてきましたが、県でも意見表明支援員(アドボケイト)を養成し、昨年10月末から、一時保護所や民間の一時保護施設などに派遣を行い、子どもの意見を聴き、関係機関と共有して支援に反映する事業を開始しています。
委託先である県公認心理師協会によると、昨年度は認定アドボケイト22名が約50名の子どもと面談し、その半数程度から意見表明があり、不安、家庭復帰や里親に関する悩み、施設内の処遇や人間関係が主な内容でした。こうした着実な取り組みに敬意を表したいと思います。
今年度の子どもの権利擁護環境整備事業は、昨年度と同等の予算が計上され、拡充をしていくこととなっています。子どもアドボカシーの対象範囲は、一時保護所、児童養護施設や里親家庭など多数の施設があるため、計画的に拡充していく必要があります。
それには、アドボケイトの人員拡充のための民間の力の活用が不可欠であり、アドボケイト育成も含めた体制の構築が急がれます。更に言えば、理念の条例化も制度の継続と社会的定着に有効ではないでしょうか。
そこで、アドボケイトの育成計画や対象施設の拡充状況、スケジュールを明確にした茨城県における子どもアドボカシーのビジョンを県民に示す必要があると思います。
また、今年4月には民間の「一般社団法人こどもアドボカシーセンターいばらき」も設立され、県民による推進機運も高まりつつありますが、依然として県内での認知度はまだ高くなく、啓発も具体策で進めるべきです。例えば、専門家による講演会や基礎講座の受講支援、関係者向けの実践的な「こどもアドボカシー・スクール」の開設なども有意義だと考えます。
以上を踏まえ、茨城県における今後の子どもアドボカシー推進のビジョンについて、福祉部長にお伺いします。
【福祉部長答弁】
子どもアドボカシーの推進に向けた県のビジョンについてお答えいたします。
こどもの意見を尊重し、権利を守る、「子どもアドボカシー」の取組は、大変重要であると認識しております。
議員ご案内のとおり、改正児童福祉法を受け、県では、こどもが自らの意見を形づくり、適切に表明できるよう支援するため、昨年
10月から、「こどもの権利環境整備事業」を実施しており、特に、こどもの今後の養育方針が決定される重要な場面であり、こどもの意向の聴き取りが必要な一時保護中のこどもを対象に、公認心理師を、意見表明等支援員、いわゆる「アドボケイト」として派遣し、実践と検証を行ってきたところでございます。
その結果、こどもの不安の解消やこども自身が今後の生活について、自らの希望を伝えることができたなど、成果が認められた一方で、意見の反映にあたり、関係先との調整に時間を要してしまうことや、支援員の活動経験が不足しているといった課題も明らかになりました。
これらの課題につきましては、意見の反映の方法について可能な限りマニュアル化を進め、迅速に対応できる体制を構築するとともに、支援員が実践経験を積む機会を増やし、人材の育成を図るなど、取組のさらなる充実に努めてまいります。
一方、こどもアドボカシーのビジョンにつきましては、まず、短期的には、本年度新たに、児童養護施設を対象施設として拡大し、実施いたしますとともに、専門機関の養成講座を活用し、さらなる支援員の養成を行うこととしております。さらに中期的には、本年3月に策定いたしました「茨城県こども計画」に基づき、施設や里親など、こどものおかれている環境に応じた適切な実施方法や訪問頻度についても検証を重ねながら、毎年度対象を広げ、計画期間内には、県内の全ての社会的養護に係る施設や里親家庭におきまして、全てのこどもたちが意見表明の機会を得られるよう、取り組んでまいります。
さらに、その実現のためには、十分な支援員の確保が必要でありますので、こどものニーズや多様性を踏まえた上で、公認心理師のほか、例えば、こどもと年齢が近い若者やこどもと接する経験が豊富な保育士など、様々な特性や強みを持つ幅広い人材の活用を図ってまいります。
また、こどもの意見を尊重するこどもアドボカシーの理念を広く社会に知っていただくことは大変意義のあることだと認識しております。
このため、今後、広報紙やホームページ、SNSなどを活用し、広く県民に紹介するとともに、関係する施設職員等を対象とした講演会を開催するなど、理解促進を図ってまいります。
なお、アドボカシーの理念の条例化につきましては、まずは、議員ご指摘の低いと言われている認知度の向上や啓発活動に注力し、その状況を鑑みて検討をしてまいりたいと存じます。
県といたしましては、こどもの意見を尊重し、こどもの最善の利益を優先することで、健やかな成長が図られるよう、こどもアドボカシーの推進にしっかりと取り組んでまいります。
【村本修司議員感想・要望】
ご答弁ありがとうございます。
今、県内でも民間による子どもアドボカシーの動きが始まりつつある今こそ、行政としてその流れを確かなものへとしていくことが重要です。対象施設の拡充や人材育成に関し、明確な計画とビジョンを県民に示すよう求めます。
また、アドボカシーは保護施設などに限らず、学校や介護施設でも重要な制度です。
県全体として、必要なところへのアドボカシーの適用を推進するよう要望します。
以下ChatGPTによる要約です。
■ 村本修司議員質問
- アドボカシーの意義と制度的背景
- 子どもが自分の意見を言える環境づくりは極めて重要。
- 改正児童福祉法により、意見表明支援事業は都道府県の業務と位置づけ。
- 県では昨年10月より、アドボケイトを一時保護所等に派遣する事業を開始。
- 現状の取り組みと課題
- 昨年度、22名の認定アドボケイトが50名程度と面談し半数が意見表明。
- 不安・家庭復帰・処遇・人間関係などが主な内容。
- 今後は対象施設(児童養護施設・里親家庭等)を計画的に拡充すべき。
- 今後の提案
- 民間の力を活用した人材育成が急務。
- 条例化による制度の定着も視野に入れるべき。
- 県民向けに育成計画や拡充スケジュールなどの明確なビジョン提示が必要。
- 啓発策として、講演会やスクールの開設を提案。
■ 福祉部長答弁
- 昨年度の実績と課題
- 一時保護中の子どもにアドボケイトを派遣し成果が見られた。
- 一方で、調整の時間や支援員の経験不足といった課題も判明。
- マニュアル整備・実践機会増加により体制を充実させる。
- 今後のビジョン
- 【短期】児童養護施設に対象を拡大し、支援員の養成も強化。
- 【中期】「茨城県こども計画」に基づき、すべての社会的養護の場で意見表明機会を保障することを目指す。
- 年齢が近い若者や保育士など、幅広い人材の活用も検討。
- 啓発と条例化について
- 広報紙・SNS・講演会を通じて認知向上に取り組む。
- 条例化は認知度向上と啓発の進捗を踏まえ検討する。
■ 村本修司議員感想・要望
- 民間での動きが出てきている今こそ、県が明確なビジョンを示すべき。
- 対象施設拡充や人材育成には具体的な計画とスケジュールの提示が不可欠。
- アドボカシーの活用は保護施設だけでなく、学校や介護施設にも拡大すべき。
#茨城県議会 #日立市

