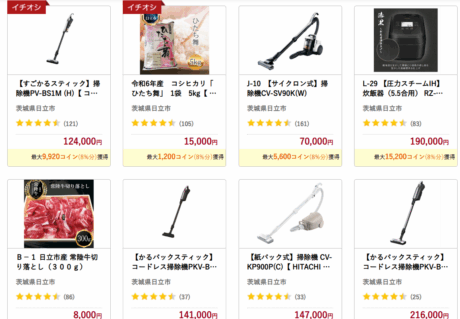宇都宮市で県外調査/未来を拓く新たな茨城づくり調査特別委員会

9月8日、「未来を拓く新たな茨城づくり調査特別委員会」の県外調査に参加しました。今回は栃木県宇都宮市を訪れ、栃木県議会と交通未来都市うつのみやオープンスクエアを視察しました。
栃木県議会では、県政の基本指針となる「とちぎ未来創造プラン」の次期計画について、検討会での取組状況を伺いました。また、地域経済の成長と発展を目指す「フードバレーとちぎ推進協議会」の活動内容についても説明を受け、産業振興の方向性や課題について意見交換しました。栃木県が「食」をキーワードに地域産業を元気にしようと取り組んでいる姿勢は、茨城県にとっても参考になる点が多く、大変学びの多い時間となりました。
その後、交通未来都市うつのみやオープンスクエアを訪問し、宇都宮市が推進する次世代型路面電車LRT「ライトライン」事業の概要について説明を受けました。さらに、実際にライトラインに乗車し、公共交通を中心としたまちづくりの可能性を肌で感じることができました。LRTがもたらす移動の利便性向上と環境負荷の低減、都市のコンパクト化といった効果は、これからの地方都市づくりに大きな示唆を与えてくれると感じました。
今回の調査を通じて、栃木県や宇都宮市の先進事例を茨城県の将来像にどう活かすかが問われます。県民の皆さまにとってより良い未来を実現するため、委員会での提言にしっかり反映させてまいります。
【参考】宇都宮市のLRT「ライトライン」について

宇都宮市が推進する次世代型路面電車(LRT)「ライトライン」は、地域の暮らしと都市構造を静かに、しかし着実に変え始めています。
2023年8月の開業から2年、JR宇都宮駅東口から芳賀・高根沢工業団地まで約14.6kmを結ぶこの路線は、低床で乗り降りしやすく、走行音も静かなHU300形の連接車が19の停留場を結び、通勤・通学や買い物、観光の足として定着してきました。全国的にも珍しい「完全新設」のLRTとして開業した意義は大きく、公共交通を軸に拠点をネットワークする“ネットワーク型コンパクトシティ”の要(かなめ)として位置づけられています。
実際の利用状況も力強い数字が続きます。開業からの累計利用者は2025年8月に1,000万人を突破。当初想定より半年早い達成で、平日は通勤・通学で混み合い、休日も沿線イベントをきっかけに需要が伸びています。沿線の回遊性が高まり、中心市街地と東部エリアを無理なく結ぶ新しい“動線”が市民の生活の質を底上げしていることがうかがえます。
まちづくりの視点でも、LRTは単なる移動手段に留まりません。宇都宮市は、歩いて楽しい都心空間の形成やバスとの結節強化、駅前の賑わいづくりなど、公共交通と一体の都市整備を一歩ずつ進めています。LRTの情報発信拠点「交通未来都市うつのみやオープンスクエア」では、ライトラインと連携したまちづくりの全体像を体験的に学べる展示が整えられ、来場者や視察の受け皿として機能しています。
そして、次の一歩が「西側延伸」です。現在、JR宇都宮駅を東西に貫く構想が具体化しており、宇都宮駅東口から都心部(教育会館付近)までの約5kmを“整備区間”として先行させ、早期開業をめざす方針が示されています。最大のハイライトはJR宇都宮駅の横断。駅ビル北側で新幹線高架(3階)と在来線(1階)の間の2階レベルを高架の軌道で通し、東西の乗り換え利便性を一気に高める大胆な計画です。これに合わせ、都心大通りの交通空間再編やバス路線の再編、交通結節点の強化(JR西口や東武宇都宮駅周辺)など、面的な交通ネットワークづくりが段階的に進みます。
ライトラインは「便利な新路面電車」という域を超え、都市の形を変えるインフラとして、日々の暮らしと地域経済を同時に押し上げる存在になっている、ということです。西側延伸が実現すれば、JR・東武・バス・LRTの結節が強まり、都心の歩行回遊や沿線の投資・雇用にも好循環が広がります。宇都宮発の挑戦は、地方都市が「持続可能な足」と「にぎわい」を両立させるうえでの現実的解を示し続けています。